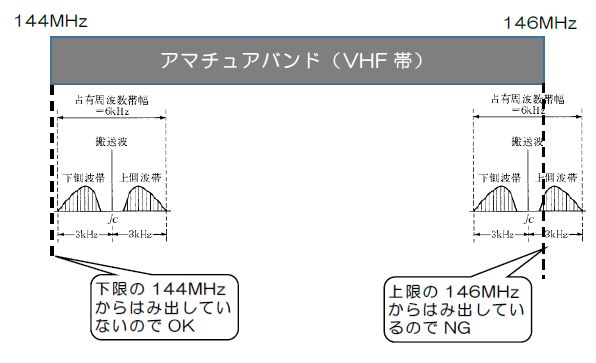| Q符号 |
意義 |
| 問い |
答え又は通知 |
| QRA |
貴局名は、何ですか。 |
当局名は、……です。 |
| QRH |
こちらの周波数は,変化しますか。 |
そちらの周波数は,変化します。 |
| QRK |
こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,どうですか。 |
そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の明りよう度は,
1 悪いです。
2 かなり悪いです。
3 かなり良いです。
4 良いです。
5 非常に良いです。
|
| QRL |
そちらは,通信中ですか。 |
こちらは,通信中です(又はこちらは,……(名称又は呼出符号)と通信中です。)。妨害しないでください。 |
| QRM |
こちらの伝送は,混信を受けていますか。 |
そちらの伝送は,
1 混信を受けていません。
2 少し混信を受けています。
3 かなり混信を受けています。
4 強い混信を受けています。
5 非常に強い混信を受けています。
|
| QRN |
そちらは,空電に妨げられていますか。 |
こちらは,
1 空電に妨げられていません。
2 少し空電に妨げられています。
3 かなり空電に妨げられています。
4 強い空電に妨げられています。
5 非常に強い空電に妨げられています。
|
| QRO |
こちらは,送信機の電力を増加しましようか。 |
送信機の電力を増加してください。 |
| QRP |
こちらは,送信機の電力を減少しましようか。 |
送信機の電力を減少してください。 |
| QRQ |
こちらは,もつと速く送信しましようか。 |
もつと速く送信してください(1分間に……語)。 |
| QRR |
そちらは,自動機使用の用意ができましたか。 |
こちらは,自動機使用の用意ができました。1分間に……語の速度で送信してください。 |
| QRS |
こちらは,もっとおそく送信しましようか。 |
もっとおそく送信してください(1分間に……語)。 |
| QRT |
こちらは,送信を中止しましようか。 |
送信を中止してください。 |
| QRU |
そちらは,こちらへ伝送するものがありますか。 |
こちらは,そちらへ伝送するものはありません。 |
| QRV |
そちらは,用意ができましたか。 |
こちらは,用意ができました。 |
| QRW |
こちらは,……に,そちらが……kHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知しましようか。 |
……に,こちらが……kHz(又はMHz)で彼を呼んでいることを通知してください。 |
| QRX |
そちらは,何時に再びこちらを呼びますか。 |
こちらは,……時に(……kHz(又はMHz)で)再びそちらを呼びます。 |
| QRZ |
誰がこちらを呼んでいますか。 |
そちらは,……から(……kHz(又はMHz)で)呼ばれています。 |
| QSA |
こちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,どうですか。 |
そちらの信号(又は……(名称又は呼出符号)の信号)の強さは,
1 ほとんど感じません。
2 弱いです。
3 かなり強いです。
4 強いです。
5 非常に強いです。
|
| QSB |
こちらの信号には,フェージングがありますか。 |
そちらの信号には,フェージングがあります。 |
| QSL |
そちらは,受信証を送ることができますか。 |
こちらは,受信証を送ります。 |
| QSO |
そちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は中継で)通信することができますか。 |
こちらは,……(名称又は呼出符号)と直接(又は……の中継で)通信することができます。 |
| QSP |
そちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継してくれませんか。 |
こちらは,無料で……(名称又は呼出符号)へ中継しましよう。 |
| QSU |
こちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答しましようか。 |
その周波数(又は……kHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信又は応答してください。 |
| QSW |
そちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信してくれませんか。 |
こちらは,この周波数(又は……kHz(若しくはMHz))で(種別……の発射で)送信しましよう。 |
| QSX |
そちらは,……(名称又は呼出符号)を……kHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取してくれませんか。 |
こちらは,……(名称又は呼出符号)を……kHz(又はMHz)で又は……の周波数帯若しくは……の通信路で聴取しています。 |
| QSY |
こちらは,他の周波数に変更して伝送しましようか。 |
他の周波数(又は……kHz(若しくはMHz))に変更して伝送してください。 |
| QTC |
そちらには,送信する電報が何通ありますか。 |
こちらには,そちら(又は……(名称又は呼出符号))への電報が……通あります。 |
| QTH |
緯度及び経度で示す(又は他の表示による。)そちらの位置は,何ですか。 |
こちらの位置は,緯度……,経度…(又は他の表示による。)です。 |